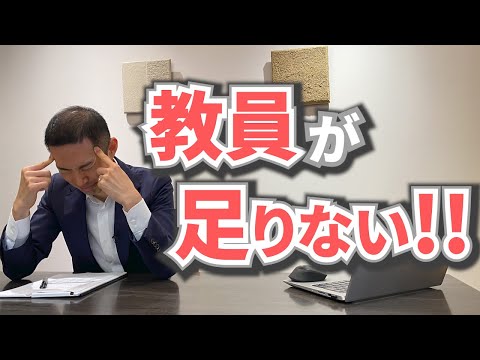文部科学省が発表した令和5年度の概算要求について、教員志望者にとって気になるトピックを解説します。概算要求を通して、今後の学校がどのように変化していくのかを見ていきましょう。
1. そもそも概算要求とは?
概算要求とは、各省庁が財務大臣に対して提出する、翌年度に必要な経費の要望です。「こういったことにこれくらいの予算を使いたい」という意向を示すもので、この要求がそのまま予算として認められるわけではありません。概算要求を受けた後、財務省が内容を精査し、「本当に必要か」を判断した上で予算案が作成されます。
2. 令和5年度概算要求のポイント①:教員定数の増加
今回の概算要求の大きなポイントの一つは、教員定数の増加です。文部科学省は、定数を5158名増やすことを要求しています。その内訳は、「小学校における35人学級の推進」「小学校高学年の教科担任制の導入」、そしてその他の「教育課題への対応」となっています。
特に小学校における施策が中心となっており、「小学校における35人学級」は現在小学3年生まで実施されていますが、令和5年度には小学4年生まで拡大される予定です。1クラスの生徒数が減ることでクラス数が増加するため、それに伴い教員数も必要となります。この35人学級は、今後小学6年生まで段階的に拡大していくことが決まっています。
また、「教科担任制」も小学校における取り組みです。小学校教員は基本的に全教科を指導しますが、外国語の教科化など、学ぶ内容が以前より専門的になっていることを受け、主に外国語、理科、算数、体育の指導教員を増やすことが求められています。
3. 令和5年度概算要求のポイント②:外部スタッフの活用
働き方改革に関する予算も今回の大きな目玉です。特に注目すべきは、外部スタッフの活用です。具体的には、教員業務支援員、学習指導員、部活動指導員の配置が挙げられます。
教員業務支援員には103億円、学習指導員には50億円と、昨年度と要求額はさほど変わりません。しかし、部活動指導員には昨年の2倍弱となる24億円が要求されており、部活動問題への対応を強化する姿勢が明確に示されています。※部活動支援員はスポーツ庁・文化庁の事業として行われます。部活動の地域移行も進んでいるため、文部科学省としても力を入れたい分野と言えるでしょう。この予算で、部活動支援員21,000人分の確保が見込まれています。
4. 令和5年度概算要求のポイント③:校務のデジタル化
GIGAスクール構想関連の施策も引き続き推進されます。今回は162億円ほどの予算が要求されています。今年度新たに要求された事業として、「リーディングDXスクール(3億円)」と「次世代の校務デジタル化(10億円)」が挙げられます。
「リーディングDXスクール」は、GIGAスクール構想の拠点となるべき学校で、全国で100校ほど設置される見込みです。タブレット等を用いた教育に関して、技術面や教育内容で他校へのモデルとなるような取り組みを発信し、STEAM教育などの教科横断型の取り組みを開発するなど、他校に先駆けて先進的な取り組みを行う役割を担います。GIGAスクール構想で1人1台端末環境が整備されたことを受け、今後はその効果的な活用が課題となります。学校によって活用方法に差があるため、全体の活用レベルの底上げが急務となっています。
「次世代の校務デジタル化」は、働き方改革にもつながる重要な施策です。校務のデジタル化自体は全国の学校に広まっていますが、現状では校内の閉鎖されたネットワーク内で処理されているため、他の教育システムとの連携や校外での操作ができないなど、不便な点が多くあります。例えば、同じ情報を異なるシステムに二重入力しなければならないといった非効率な作業が発生しています。また、学校ごとに異なるシステムが利用されているため、人事異動時の対応なども課題となっています。そこで、データをクラウド化なども考慮した全国レベルの汎用システムの構築が検討されています。
5. 令和5年度概算要求のポイント④:ギフテッド教育
他の施策に比べると要求額は少ないものの(1億円)、ギフテッド教育の取り組みが盛り込まれた点も注目すべきです。文部科学省は「特定分野に特異な才能のある児童生徒」と表現していますが、これは例えば、知性が非常に高かったり、特定の分野に突出した才能を持っていたりする子どもたちに対する教育を指します。
これまで、そのような子どもたちは、その才能ゆえに周囲に理解されず、苦しむケースがありました。
(文部科学省資料より抜粋)
- 発言をすると授業の雰囲気を壊してしまうと感じ、分からないふりをしなければならず苦痛を感じた。
- 鉛筆で文字を書く速度と脳内での処理速度が釣り合わず、プリントでの学習にストレスを感じていた。
- 同級生との話がかみ合わず、大人と話している方が良い。変わっている子扱いされる。
- 先生の間違いを指摘してもすぐに分かってもらえず悔しい思いをする。先生の矛盾した指導に納得がいかない。
参考:特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関する有識者会議アンケート結果まとめ https://www.mext.go.jp/content/20211105-mext_kyoiku02-000018576_01.pdf
このような状況を踏まえ、まずはそのような子どもの理解を深め、取り組み事例を集めることから始めるそうです。
6. まとめ
今回は、文部科学省の概算要求の中から、特に学校教育に関する部分を解説しました。これらの情報が、今後の学校教育がどのような方向に進もうとしているのかを考える上で、少しでもお役に立てれば幸いです。



 前の記事へ
前の記事へ