
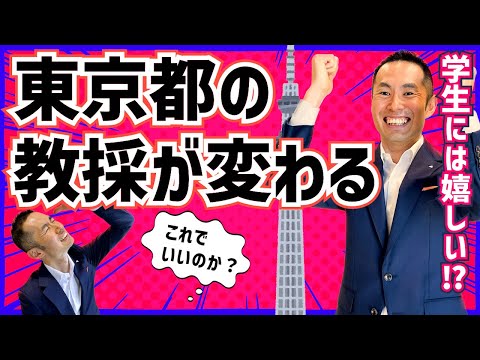
今回は、深刻化する教員不足の現状、その要因、そして現在進められている対策について詳しく解説します。
教員不足という言葉は、文部科学省(以下、文科省)が2024年1月に発表した「教師不足に関する実態調査」をきっかけに広く知られるようになりました。この調査によると、2021年5月1日時点で全国2,065名の教員が不足しており、教員不足となっている学校は1,591校に上ることが明らかになりました。特に小中学校での不足が目立っており、全体の8割以上を占めています。この調査結果は5月1日時点の状況を示しているため、その後も不足状態が続いている学校があることが推測されます。
都道府県別に見ると、教員不足の状況には差があります。小学校を例に取ると、特に教員不足が深刻なのは島根県で、教員不足率が全国で最も高い1.46%でした。次いで熊本県が0.88%、鳥取県が0.81%と続きます。一方、当時不足率が0だった自治体は、山形、群馬、東京、新潟、和歌山、山口のわずか6都県でした。教員不足は人口の少ない過疎地で起こっていると思われがちですが、実際には地方だけの問題ではないことが分かります。
※動画で日本地図を掲載できる場合は、不足率を色分けした地図を掲載すると視覚的に分かりやすくなります。
出典:「教師不足」に関する実態調査~文科省
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/mext_00003.html
教員不足の要因として、以下の点が考えられます。
(ア) 見込み数以上に教員が必要だった
教員不足の要因の一つとして、産休や育休、病休取得者、そして特別支援学級へのニーズが教育委員会の見込み以上に増加したことが挙げられます。これらの欠員を補充するための臨時的任用教員の数が増加しました。
(イ) 非正規教員(臨時任用・非常勤講師)人数の減少
何らかの理由で休む教員の代わりに教壇に立つ、臨時任用や非常勤講師の人数が減少していることも要因の一つです。その理由としては、以下の点が考えられます。
(ウ) 非正規教員率の上昇
教員定数に対する非正規教員割合の高さも、教員不足の要因の一つと言われています。文科省が発表した2020年度の教員定数に対する正規教員の割合を見ると、自治体ごとに大きなばらつきがあります。正規教員の割合が最も大きいのは東京都で104.5%となり、正規教員だけで教員定数を上回っています。一方、最も小さいのは沖縄県で、教員の約5.8人に1人が非正規教員でした。正規教員の割合が低いということは、臨時任用や非常勤講師に頼っているということになるため、講師名簿登録者が減少するとその影響を強く受けてしまいます。沖縄県の教員採用試験の倍率は全国的に高い方ですが、このような背景が教員不足を引き起こしている要因の一つと考えられます。
この非正規教員の問題には、2001年の義務標準法(公立義務教育諸学校の学級編制および教職員定数の標準に関する法律)の改正で導入された、いわゆる「定数崩し」という政策が影響を与えています。この改正により、各自治体の定数に対する非正規教員の割合が高くなりました。
■定数崩しとは
教員の給与は自治体と国がそれぞれ負担していますが、その給与に対して国の負担額を決める計算式に、非常勤講師を含めてよいことになりました(以前は常勤の職員のみが対象でした)。これは2001年の義務標準法の改正で導入されました。
出典:公立小・中学校等の教員定数の標準に占める正規教員の割合~文科省
https://www.mext.go.jp/content/20210517-mxt_zaimu-000014948_06.pdf
教員不足は、現場の教員に大きな負担を与えます。小学校では、教員不足により管理職などが教壇に立つケースも発生しています。中学校や高校でも、同じ専門科目の教員の欠員を埋めるために、他の教員が受け持つ授業数が増加します。このような状況が続くと、教員不足が解消されないまま、他の教員の負担ばかりが重くなるという悪循環に陥ってしまいます。
教員不足の影響は、児童・生徒にもおよびます。例えば、担任の先生が年に数回変わったり、代替の教員が見つからない授業が自習になったりするケースも考えられます。自習ばかりが続くと、生徒の学習の遅れにつながる可能性もあります。
教員不足を解消するために、現在以下のような対策が進められています。
(ア) 産休育休代替教員の前倒し採用
産休育休の代替教員を確保するため、文科省は年度当初に前倒しで配置する場合、少人数指導などの加配分を柔軟に活用できるようにする措置を2023年度から行うよう各教育委員会に伝えています。これにより、例えば5月から7月に産休等に入る教員の代替教員を4月に採用することが可能になります。産休等のタイミングで採用しようとすると、名簿登録者がすでに他の仕事に就いている可能性が高いため、早めに採用して配置できるようにしたということです。
(イ) 正規教員の割合を高める
教員定数に対する正規教員の割合を高めることも、2023年9月に当時の永岡文科大臣が各教育長に要請しています。
(ウ) 教採の実施時期を早める
教員採用試験の実施時期を早めることで、応募者数の増加を狙う取り組みも進んでいます。
(エ) 教員の待遇の見直し
いわゆる「ブラック職場」の原因の一つと言われている給与についても、見直しの動きがあります。自民党の萩生田政調会長(当時)が、教員のなり手不足や処遇改善について抜本的な改革案を作り上げるため、党内に「令和の教育人材確保に関する特命委員会」を立ち上げ、働き方や給与について検討する旨を表明しています。
これらの対策は主に正規教員に向けたものが多い印象を受けます。しかし、臨時任用などで現場に立っている教員は、教員採用試験に不合格だった方、または受験しなかった方々です。それでも、いわゆる正規教員とほぼ同じ仕事をしている場合もあります。そのような状況を考慮すると、非正規教員の待遇向上や雇用の安定も重要な課題と言えるでしょう。また、現場で活躍している非正規教員に対して、試験の一部免除だけでなく、教員採用試験におけるさらなる優遇措置を検討することも必要ではないでしょうか。
今回は、教員不足の現状とともに、その原因や今後の動きについて解説しました。人手不足が現場の教員や子どもたちに与える影響は大きいため、教員不足の解消に向けた取り組みが一日も早く進むことを期待します。
すべてのサービスを
無料でご利用いただけます
TEL.0120-542-764
TEL.0120-542-764