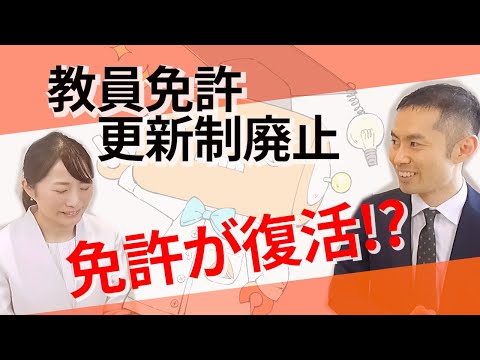今回は、教員採用試験(教採)が今後どのように変化していくのか、改革の方向性について解説します。先日文部科学省(以下、文科省)で発表された「教師の養成・採用・研修等の在り方について」の中間まとめ案で示された、採用に関する内容を中心に整理します。
1. 教師不足問題の影響
文科省は、教師不足などを深刻な問題として捉えています。2022年度採用の教採結果でも示されているように、受験者数の減少や倍率の低下は深刻です。全体の倍率は過去最低の3.7倍となりました。専任の教員になりやすくなったと言えますが、一方で受験者数の減少は臨時任用や非常勤講師の人数に影響を与え、産休や育休、病休等の代替教員が見つからないという、いわゆる教師不足につながります。
2. 教員採用試験の方向性
文科省は、教採に関して主にスケジュールと試験内容を変える必要があると考えているようです。「受けやすくする」という点が重視されている印象を受けます。
(1) スケジュール
試験の実施時期を早める方向で検討されています。現在の教採スケジュールは大まかに、4・5月に出願、7月に一次試験、8月に二次試験、10月に合格発表という流れです。この時期を早めようというものです。
試験時期を早める理由の一つは、学生の就職活動状況です。民間企業の就職活動は開始も内定時期も早まっており、内々定の解禁日とされている6月1日前に就職活動を終えている学生もいます。特に中高の採用試験は民間の影響を受けやすいと言われています。中高の教員免許は教育学部でなくても取得できるため、教員免許を取得することが卒業要件に含まれていない学生のうち、教員免許を取得した人でも教員になった人は約34%というデータもあります。※
明確な時期の目安は示されていませんが、大学3年生から受験できるようにするという意見があるようです。永岡文部科学大臣も大学3年生からの受験を検討していることを話していました。
新卒者だけでなく、民間企業経験者を意識した動きもあります。民間企業経験者向けの選考を夏だけでなく、秋や冬にも実施できるように進めていくべきという意見もあります。民間企業で働いている人の中には、夏に都合がつかない人もいるため、教採の時期が複数あることで転職者のニーズに応えられる可能性があります。
※出典:令和3年度「教師の養成・採用・研修の一体的改革推進事業」教職の魅力向上に関する取り組みの推進教職課程を置く大学等に所属する学生の教職への志望動向に関する調査
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/sankou/1409999_00002.htm
(2) 試験内容
試験内容についても、受験のしやすさが検討されています。例えば、民間企業の就職活動をしている人の併願も考慮し、民間の適性検査(例:SPIなど)の利用が検討されています。今年、さいたま市の教採でSPI3が利用されましたが、今後他の都道府県でも行われるようになるかもしれません。
教員免許更新制度が廃止されたため、受験者を増やしたいという意図もあります。現在、公立学校の採用者で民間企業経験者は1000人強で約4%と少ない状況です。この割合を増やしていくことが目標となっています。
その他には、現在民間企業でインターンシップが採用時に活用されているように、教育実習や教師養成塾などでの活動成果を選考に活用することも考えられています。学習指導要領や大学入試も変化していく中で、教採の内容も変化していく必要があり、思考力・表現力・判断力等を評価する試験問題の検討も進められています。
(3) 正規教員の割合設定
採用に関わる点では、2023年9月末に永岡大臣が各教育庁に要請した、正規教員の割合の目標を設定することも挙げられます。教員には専任教諭と呼ばれる正規教員と、臨時任用や非常勤講師などの非正規教員がいます。各都道府県で正規教員の割合の目標値を設定することで、教師不足に歯止めをかけようという目的があるようです。教師不足の直接的な理由は臨時任用等の教員不足であり、専任教諭が休んだ場合の代替教員が見つからないという事態を防ぐために、専任教諭の割合を上げるという考え方です。これにより、教員採用試験の合格者が増える可能性があります。ただし、退職者の数との兼ね合いもあるため、一概に増えるとは言い切れません。
3. まとめ
今回の内容から、文科省が多くの人に教採を受験してほしいと考えていることが分かります。少子化が進む中で、学校に限らず採用する側は優秀な人材の獲得競争が激しくなっています。「中間まとめ案」にも、
任命権者である各都道府県・指定都市教育委員会等では、「選ぶ側」であると同時に「選ばれる側」であることを強く意識し、優れた人材を確保できるようにするための教員採用等の在り方の見直しに取り組むことが必要である。
という記載があります。選ばれるためには、教採の内容だけでなく、教員の働き方など、他の分野の見直しも必要不可欠です。受験のしやすさだけでなく、教員という職業の魅力自体を高めることが重要と言えるでしょう。
<参考URL>
中央教育審議会 「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会 中間まとめ(案)https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/1422489_00003.html



 前の記事へ
前の記事へ