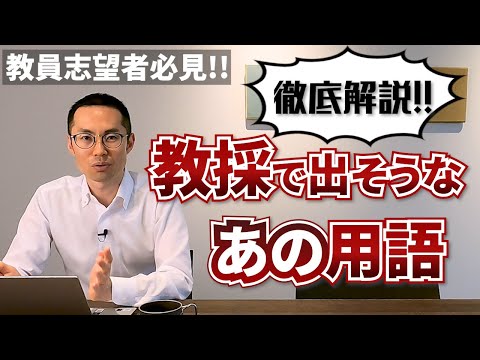文部科学省(文科省)から令和7年度の概算要求が発表されました。今回の記事では、議論の的となっている教職調整額を中心に、文科省と財務省の考え方を整理し、今後の動向を探ります。
1. 学校の働き方・処遇に関する概算要求
- 教員の人件費関係: 1兆5807億円(令和6年度予算+180億円)
- 支援スタッフの充実: 165億円(+40億円)
- 教師人材の確保強化: 7億円(+2億円)
2. 教師の待遇改善:教職調整額の引き上げが焦点(+232億円)
文科省は教師の待遇改善として、以下の点を概算要求に盛り込んでいます。
- (ア) 教職調整額の引き上げ: 現行の月額給与の4%から13%への大幅引き上げを要求。
- 今回の概算要求では、2026年1月~3月分を計上しています。自治体の条例改正などに時間がかかることが主な理由です。その他、学級担任や管理職への手当の充実も図られる予定です。
3. 教職調整額を巡る文科省と財務省の対立
教職調整額の引き上げに関して、財務省は文科省とは異なる案を提示しています。
- (イ) 財務省案:
- 教職調整額は、10%を目標に段階的に引き上げる。
- 将来的には時間外勤務を月20時間程度まで減らし、教職調整額を10%に引き上げた段階で、時間外勤務手当を支払う制度に移行する。
- 授業以外の業務時間の削減や長期休暇の取得などの働き方改革を進め、教員の時間外勤務の全国平均が国の目標値を下回れば、翌年度の調整額を段階的に引き上げることを提案。
- 財務省は、13%への引き上げを求める文科省案に対し、以下の点を批判。
- 実効性のある学校業務の縮減策と連動していない。(中央教育審議会が時間外在校等時間を月20時間程度にすることを目標としているにもかかわらず、13%=月26時間分を要求しているのは矛盾があるのではないか?)
- 各教員の在校等時間に差があるにもかかわらず、その差に応じたメリハリがない。(時間外在校等時間が0時間の人も、26時間分が支給されるのは不公平ではないか?)
- 上記の問題を抱えているため、必ずしも教職の魅力向上に繋がらず、効果に乏しい。
- 教職調整額を4%から13%に引き上げる場合に必要とされる年間5600億円程度の公費の安定財源も示されていない。
- 財務省案の背景には、教員が担っている業務には、やりがいの小さい業務や負担感の大きい業務があるため、まずは担う業務を減らし、減らした後の状況に合わせた給与を支払うという考え方がある。
| 項目 | 文科省案 | 財務省案 |
| 教職調整額 | 2026年1月から13%へ引き上げ | 10%を目標に段階的に引き上げる |
| 調整額引き上げの条件 | 特になし | 時間外勤務の全国平均が国の目標値を下回る |
| 時間外労働の考え方 | 給特法の考え方を維持(超勤4項目以外は「自発的行為」) | 2030年度をめどに時間外勤務とすることも視野 |
文科省は財務省の案に対し、以下の点を反論しています。
- 教職員定数等の充実をすることなく、単に学校現場の業務縮減の努力のみをもって学校における働き方改革を進めようとするものであり、学校現場への支援が欠如している。
- 学校や地域の状況がさまざまである中、いじめや暴力行為への対応等、予見不可能な必ず対応しなければならない業務が多く発生している。勤務時間の縮減を給与改善の条件とすれば、必要な教育活動を行うことがためらわれ、学校教育の質の低下につながる。
- 仮に時間外勤務手当化されれば、勤務時間外の業務に逐一管理職の承認が必要になるなど、教師の裁量が著しく低下し、創意工夫を発揮しにくくなる。
- 時間外勤務手当の国庫負担に上限を設けることは、自治体に負担を転嫁するもの。義務教育に対する国の責任を果たせず、自治体の財政力の差によって教育活動の量に差が生まれ、教育格差が生じる。
- 学校における働き方改革は、これまで以上にスピード感をもって進めていく必要があるが、高度専門職である教師にふさわしい給与にすることが喫緊の課題。
4. 教職員定数の増員要求
文科省は教職員定数についても増員を要求しています。
- 小学校での教科担任制の拡充:+2,160名
- 小学校高学年だけでなく、中学年にも教科担任制を進めるため:+1,750人
- 新任の先生の持ち授業時数軽減のため:+410人
- 35人学級の推進:+3,086人(小学校全学年で35人学級を実現する予定)
- 小学校以外のプラスも含めると、予算を設けて合計で7,653人増える見込み。一方で学級数の減少や小中学校の統廃合などによる教職員定数の削減(自然減)があり、その数は8703人。そのため、総数では1,000人減ることになる。
5. 支援スタッフの強化:165億円
支援スタッフの強化は、教員の負担軽減に直結する重要な施策です。令和7年度概算要求では、以下の3種類のスタッフの拡充が求められています。
- 教員業務支援員:110億円
- 教員の多忙化解消のため、学習プリントの準備、来客・電話対応、行事準備の補助など、教員が本来の業務に集中できる環境整備を目的としています。
- 副校長・教頭マネジメント支援員:16億円
- 副校長・教頭の業務負担軽減を目的とし、教職員の勤務管理事務の支援、施設管理、保護者や外部との連絡調整、学校徴収金等の会計管理などを担当します。特に、今年の予算が5億円だったことから、3倍の予算増(1000人→3000人)となっており、副校長・教頭の働き方改革に重点が置かれていることが伺えます。退職教員、教育委員会勤務経験者、民間企業等での事務経験者など、多様な人材の活用が想定されています。
- 学習指導員:37億円
- 学習支援が必要な児童生徒への対応強化を目的としています。
6. 中学校の部活動の地域移行:69億円(昨年の倍)
中学校の部活動の地域移行は、教員の働き方改革の大きな柱の一つです。令和7年度は、地域移行に向けた改革推進期間の最終年度となり、地域移行の実施が本格化する予定です。
- 部活動の地域連携や地域スポーツ・文化クラブ活動移行に向けた環境の一体的な整備に、今年度当初予算額の2倍以上となる69億円(同37億円増)が計上されています。
- 具体的な取り組みとしては、以下の実証事業が含まれます。
- 受け皿となる地域クラブについて、コーディネーターの配置を含む運営団体・実施主体の体制整備
- 指導者の質・量の確保
- 経済的に困窮している世帯に対する参加費用の支援
- 学校施設の活用など
7. GIGAスクール構想の推進と学校DXの加速に向けた予算も大幅に拡充
GIGAスクール構想の推進と学校DXの加速に向けて、以下の予算が大幅に拡充されています。
- (ア) 通信ネットワークの改善、次世代校務DX環境の整備や自治体への伴走支援の強化:94億円
- 高速大容量の通信ネットワーク環境の整備、校務システムのクラウド化、自治体への導入支援などを推進します。
- (イ) 生成AIを含む先端技術・教育データの利活用の推進:10億円(+6億円)
- 生成AIの教育現場への導入・活用に向けた研究・調査、教育データの利活用などを推進します。
- (ウ) 小中学校での英語などのデジタル教科書の導入・活用促進:19億円(+2億円)
- デジタル教科書の効果的な活用方法の研究開発、教員研修などを推進します。
- (エ) AIの活用などによる英語教育の抜本強化:6億円(+3億円)
- AI教材の導入、教員研修などを推進します。
- (オ) 教育DXを支える基盤的ツールの整備・活用、教育データの利活用の推進:18億円(+8億円)を要望
- 教育データ標準の普及促進、データ利活用基盤の構築などを推進します。
- (カ) DXハイスクールの拡大
- 2023年に100億円の補正予算を組み、現在1000校強あるDXハイスクールを、概算要求で107億円を計上し、拡大を進めるようです。
8. まとめ
文科省の文教施策としては、
- 教職調整額と教員定数増加をメインとし、教員の待遇改善と負担軽減を目指すこと
- 部活動の地域移行の本格化
- AIも加えたGIGAスクールの環境整備
に力を入れたいと考えていることが分かります。
しかし、前述の通り、教職調整額に関しては財務省との間で意見の相違があり、今後の予算編成過程でどのような決着を見るのか、注目する必要があります。特に、今回与党が過半数割れしたこともあり、当初の予算案がスムーズに通らない可能性も指摘されています。今後の動向を注視していく必要があるでしょう。
※参考
- 令和7年度概算要求のポイント:https://www.mext.go.jp/content/20240827-ope_dev02-000037780_1.pdf
- 概算要求説明:https://www.mext.go.jp/content/20240827-ope_dev02-000037780_6.pdf
- https://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/r01/1420668_00002.html
- 財政制度分科会(令和6年11月11日開催)資料一覧:https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20241111/02.pdf
- 教育新聞:https://www.kyobun.co.jp/article/2024082901



 前の記事へ
前の記事へ