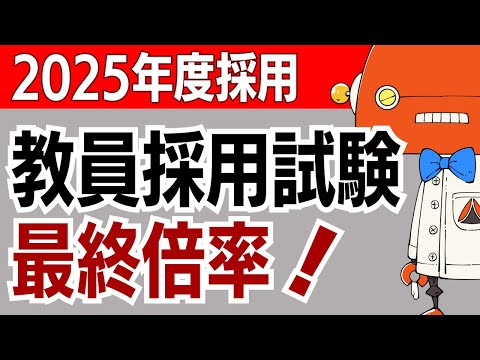ニュースでも話題になっている学校の働き方改革の一つ、「部活動改革」、特に「部活動の地域移行」について取り上げたいと思います。これは教員の働き方を含め、今後の学校教育に大きな変化をもたらす可能性のある取り組みです。ぜひ現状を確認していきましょう。
1. 部活動の地域移行とは?
そもそも「部活動の地域移行」とは何でしょうか?
これは文部科学省が進めている取り組みで、文字通り学校で行われている部活動を地域で行うようにしようというものです。具体的には、中学校の休日の運動部・文化部の活動が2023年度から徐々に学校の手を離れ、地域に移行する予定です。
現在のところ中学校が対象となっていますが、将来的には高校も対象とするようです。なお、これは公立学校の動きであり、私立学校は独自で対応することになりそうです。
2. 部活動の地域移行の理由~働き方改革
地域へ移行する理由は大きく2つ挙げられます。1つは学校の働き方改革の一環であること、もう1つは少子化に伴う生徒数の減少です。
学校の働き方改革は、すでにニュースなどで耳にしていることと思います。文部科学省が2016年に行った調査(小中学校教員の勤務実態調査)で、中学校教員の約6割が月80時間を超える残業をしていることが判明しました。また、土日に部活動をしている時間は、2006年は1時間6分だったのに対し、2016年は2時間10分と約2倍になっていたそうです。
学校の働き方改革を進めるにあたり、教員の業務の整理が行われました。その際、部活動は「学校の業務だが、必ずしも教師が担う必要のない業務」とされました。
3. 部活動の地域移行の理由~少子化
文部科学省の調査では、公立中学校の学校数は1990年の11,275校から2021年は10,076校と約1割減っています。また、生徒数は1990年が約537万人でしたが、2021年は約322万人と約4割も減っています。
今後は学校単位で生徒がいなくて部活動ができないケースが増加する可能性が高くなります。そこで、生徒たちの活動機会を確保するために、部活動を学校の外で実施し、希望する多くの生徒が学校を超えて参加できる機会を作ろうという考えもあります。
4. 部活動の地域移行の課題
地域移行の課題が全くないわけではありません。現在挙げられている主な課題として、「学校に代わりどこが実施するのか(実施主体)」「指導者の量や質は確保できるのか」「会費の負担」「大会に出場できるか」などが挙げられます。
実施主体の課題は、部活動運営をどのような機関が行うかということです。これまでは良くも悪くも指導も管理も学校に任せておけばよかったのですが、地域移行になると、指導や管理をどこが行うかが課題となります。
地域のスポーツ団体や文化芸術団体など、さまざまな団体が候補に挙がっています。しかし、地域によってそれらの団体の有無や活動状況に差があることが明らかになってきました。
指導者の量と質に関しては、そもそも指導できる人材を確保できるのかという問題があります。政府によると、2020年度の公立中学校の部活動指導員の人数は5,891人だったそうです。実はその年度の予算では1万200人を見越して11億円を計上していたそうです。つまり見込みの6割ほどしか確保できなかったということになります。
部活動改革を所管しているスポーツ庁によると、「配置された人数が予算の見込みよりも少ないのは、自治体が人材確保に苦慮している面もあるが、部活動指導員が働く時間が想定よりも長くなっていることもある」と説明しています。
質の面では、現在の部活動は学校にいる教員が指導することが多いため、生徒や保護者もある程度安心できる部分もありました。しかし、学校外の人が指導する場合、その指導者の質をどのように担保するかも課題になります。その解決策として、研修や資格の取得などが挙げられています。ですが、これまでも教員はなじみのない分野の部活動の顧問をすることが多く、専門性の観点ではクリアできるかもしれません。生徒への指導方法等は補う必要はあるかもしれません。
外部の方が部活動に関わるということは、お金も問題になります。特に保護者はお金について気になるかもしれません。今は、部活動は用具代などを除くと、大きな金銭的負担は生徒・保護者にはありません。しかし、外部機関等が行うことになると当然、指導料や月謝などの会費が発生します。もし金銭的負担が大きくなると、それを理由にスポーツ活動や文化活動への参加をためらう生徒が出てくるかもしれません。
地域移行した場合、学校単位だけでなく地域の団体の参加も考えられますが、主催している団体の規定によっては参加が制限される場合もあります。
そのため、各団体は対応しつつあります。中体連(日本中学校体育連盟)は主催大会の参加規定を変更し、地域のスポーツ団体も参加できるようにしました。全日本吹奏楽連盟と全日本合唱連盟も大会への参加資格を見直し、中学生が所属する地域の団体も参加できる方向で検討していることを明らかにしています。全国大会などの大会は、少子化の影響で学校単位での参加が難しくなっている現状があります。このような状況が改善されると良いですね。
スポーツも文化活動も地域ごとに活動の程度に違いがあります。そのため、地域格差が問題になる可能性があります。大都市であれば大抵の活動や指導者がいるかもしれませんが、そうでない地域もあります。地域によっては、移行はしたいがお願いできるところや人がいないということも起こり得ます。
5. 教員志望者への影響
仮にこの取り組みが進んでいくと、土日だけでなく平日の部活動も移行される可能性があります。そうなると、少なくとも教員が部活動に費やす時間が減るので、教員個人の負担軽減につながります。
勤務状況で教員になることを悩んでいた方にとっては、教員を目指しやすくなります。一方で、教員の方や教員志望の方の中には、部活動指導にやりがいを感じている方もいます。そのような場合、今までと異なるモチベーションで学校勤務をする必要が出てきます。
6. まとめ
今回は学校の働き方改革の一つ、「部活動の地域移行」についてお話してきました。今回の施策は、教員の勤務状況の改善につながるものです。また、今まで当たり前だと思っていた部活動の在り方が大きく変わる可能性が高く、教員の働き方に大きな影響を与えるものです。ぜひ今後の動きにも注目していきたいと思います。



 前の記事へ
前の記事へ