
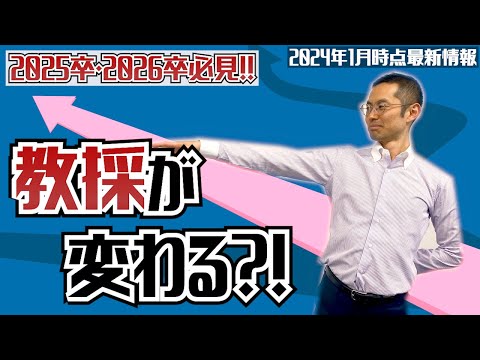
今回は、今年(2023年度採用)行われた教員採用試験の結果から見えてきた各自治体の状況を詳しく見ていきましょう。
今年行われた教員採用試験の平均倍率(政令指定都市を除く)は約3.3倍となりました。東北や近畿、四国あたりは比較的倍率が高く、関東や九州は低い自治体が目立ちます。
小学校の平均倍率は約2.2倍と、全体と比べると低くなっています。2倍を切っている自治体は24あり、全国の半分を占めています。東北や九州で特に低く、関東では東京とその近県で低く、周辺部で比較的高くなっています。
中学校の平均倍率は約3.7倍と、全体や小学校よりも高くなっています。九州で特に低く、四国や近畿で比較的高くなっています。
高校の平均倍率は約5.9倍と、全体、小中よりも高くなっています。四国で比較的高く、東北や九州も比較的高いエリアがあります。
東京の中高は、教科によって倍率に差があります。保健体育は6.2倍、社会の公民は4.9倍と比較的高めなのに対し、英語は1.8倍、理科の物理は1.6倍と小学校と同じくらい低い状況です。
計算方法によっては、1倍を切る自治体もあります。例えば大分県では、県が発表している合格結果の小学校の部分を見ると、
となっており、受験者数ですでに1倍を切っている状態です。人数としては全員合格という状況でしたが、実際はそうもいかないようです。同様の状況は秋田県の小学校でも見られました(採用予定者130名に対し一次受験者150名、合格者118名)。
今年の教員採用試験の状況を見てきました。先日文科省から発表された昨年度実施の教採も低倍率が目立ちましたが、今年度実施も特に小学校の倍率は低くなる傾向が見られます。一方で、中学・高校も以前よりは低いものの、それなりの倍率となっています。
採用する側としては、試験の結果が必ずしも良くない人も合格を出さざるを得ない状況かもしれません。仮に教採で不合格だったとしても、期限付き任用などで採用される可能性が高くなっています。現在、教採の改革や学校の働き方改革を進めようという動きがあるため、これらの取り組みが進み、多くの方が教員を目指す状況になることが期待されます。
受験する側としては、場合によってはチャンスと言えるかもしれません。教採に合格するために、低倍率の分野に挑戦するという戦略もあります。しかし、あまり自分に合わない学校や地域だと、採用された後に苦労する可能性もあります。自分の希望などを考慮して受験戦略を立てることが重要です。すでに自治体によっては来年度実施の教採説明会が行われているため、引き続き情報収集を行い、試験勉強などを進めていきましょう。
すべてのサービスを
無料でご利用いただけます
TEL.0120-542-764
TEL.0120-542-764