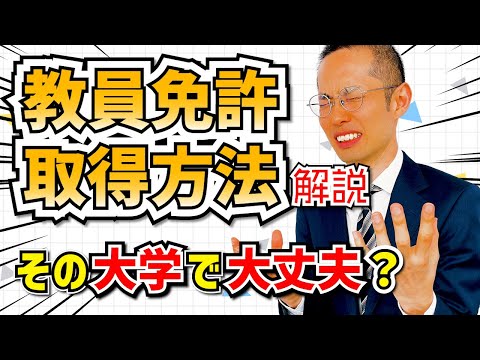今回は、議論が進んでいる教員免許の今後について解説します。文部科学省で発表された「教師の養成・採用・研修等の在り方について」の中間まとめ案で示された、教員免許に関する内容を中心に見ていきましょう。すでに行われていること、これから検討されることを整理することで、教員免許取得の将来像を明らかにします。
1. すでに行われていること
教員免許に関して、すでに変化が起きています。最も大きな変化は、教員免許更新制度の廃止です。この制度は現職教員にとって講習等の負担となり、教員ではない方にとっては未更新状態が教員への道を阻む要因となっていました。この廃止によって、制度上の障壁が取り除かれたと言えるでしょう。
また、特別免許状の授与がしやすくなったことも重要な変化です。特別免許状とは、特定の分野で豊富な経験や知識、技術を持つ方を「教諭」として迎え入れるために、都道府県が発行する免許状です。この免許状があれば、他の教員と同様の業務を行えます。ただし、発行された都道府県でのみ有効という特徴があります。実際に、塾講師がこの免許状を活用して教員になる事例、外国籍の方が免許を取得した事例も存在します。
特別免許状の授与要件も緩和されました。以前は、教科に関する業務を600時間以上行った、または、教科に関する専門分野に関わる業務を3年以上行ったなどの要件がありましたが、これらの要件が緩和されたのです。例えば、600時間という条件はすでに(2021年5月)撤廃されています。さらに、専門分野に関する業務にNPO活動等も加えられました。
2. 教員免許が2年で取れる?
教員免許の単位取得が容易になる可能性も出てきました。通常の4年制大学では、教職課程は4年間かけて単位を取得するのが一般的ですが、これが2年間で取得できるようになるかもしれません。
これは、二種免許の取得を推進する意見が出ているためです。二種免許は短大でも取得できる免許で、一種免許よりも必要単位数が少ないのが特徴です。4年制大学でも二種免許を取得しやすくすることで、教職課程を履修している学生が途中で諦めてしまうことを防ぐ狙いがあるようです。
文部科学省の調査によると、教員免許取得が卒業要件でない場合、教職課程を履修して途中で諦めてしまう学生は約20%(449/2193)に達し、そのうち約67%の学生が大学2年までに教職課程を諦めているというデータがあります。特に、大学2年で諦めてしまう学生が約40%を占めていることから、早期の段階で免許取得の道を開くことの重要性が示唆されています。※1
一種免許と二種免許では、必要単位数に差があります。二種免許が存在するのは、幼稚園、小学校、中学校です。小学校と中学校における一種と二種の最低必要単位数は以下の通りです。※2
| 一種 | 二種 | |
| 小学校 | 59 | 37 |
| 中学校 | 59 | 37 |
実際に教員になった場合、一種と二種で仕事内容に違いはありません。ただし、給与には差があるようです。
※1 https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/000181535.pdf
※2 https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/000192036.pdf
3. 試験のみで免許が取れる?~教員資格認定試験の拡大
一度社会人になると、大学で教職課程を履修すること自体が難しくなりますが、この点に対する対策も検討されています。
実は、合格すれば教員免許を取得できる試験が存在します。教員資格認定試験というもので、現在も幼稚園二種、小学校二種、特別支援学校一種の試験が実施されています。
以前は高校の教員資格認定試験も行われていましたが、現在は実施されていません。中学校の試験はこれまで実施されていないようです。しかし、高校の試験を復活させるという意見が出ています。
議論されているのは、「情報科」に限った復活のようです。GIGAスクール構想の推進に伴い、プログラミングなどに長けた人材を教員として学校で働けるようにしたいという意図があると考えられます。また、認定試験には教科に関する試験がありますが、情報関係の国家資格を有していれば免除するべきだという意見もあります。
教員資格認定試験は、筆記の一次試験と、面接や実技の二次試験で構成されています。今年度実施された小学校の試験を例に挙げると、一次試験は4種類あります。1つ目、2つ目が「教職に関する内容」と「教科に関する内容」のマークシート問題、3つ目、4つ目が「授業場面に関する内容」と「小学校教員としての理解や意欲に関する内容」に対する論述問題です。二次試験では、指導案作成や模擬授業などの実技、グループ討議や個別面接が行われ、課題論文作成も課されるようです。
試験内容は教員採用試験に近いと言えますが、大学などで教職課程を履修するよりも負担は少ないと言えるでしょう。免許を持っていなくても教員として活躍できる人材は多くいると考えられ、そのような人材に免許を取得してもらい、学校現場で活躍してもらうことが期待されています。
4. まとめ
今回は、教員免許の今後について解説しました。全体的に、免許を取得しやすくなるような動きが今後起こる可能性が高いと言えます。免許取得の機会が増えることは歓迎すべきことですが、教員免許そのものの価値が低下することのないように、制度設計が慎重に進められることを期待します。
<参考URL> 中央教育審議会 「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会 中間まとめ(案)https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2022/1422489_00003.html



 前の記事へ
前の記事へ